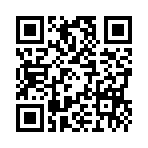2011年10月09日
三島市徳倉 八乙女神社は女性の神様です。祭典に・・。

三島市徳倉の「八乙女神社」
秋の祭典は、近隣の子供たちにとって楽しみな
お祭りです。
我が家の子供たちも、花火の音に誘われ、参加していました。
三島市、徳倉地区は第6町内会までありますが、
全部の町内が合同で、祭典を行なっています
地域のこういうお祭りを受け継いで行くことは
地域をひとつにする大事な行事だと思います。
「八乙女の舞い」は、三島市北上小学校の6年生でした。
徳倉町内の神社担当の皆様、2日間のおつとめご苦労様でした。



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 |
三島市の北方、徳倉にあり、祭神は天鈿女命(あめのうずめのみこと)で
、古くから子宝に恵まれるという安産の神様です。この女神が天(あま)の岩
戸(いわど)の前で歌舞をし、隠れた天照大神(あまてらすおおみかみ)を無
事外にお迎えしたことから芸能の神としても信仰を集めています。「うずめ」
とは、貴い女、珍しい女、美しい女の意味です。なお「お多福めん」は、日本
女性美のシンボルといわれていますが、この女神の象徴ともされています。
天正18年(1590)3月、豊臣秀吉の小田原城攻略のとき、神社も兵火をこ
うむり記録も宝物も失ってしまいました。慶長9年(1604)再建されましたが、
その由緒(ゆいしょ)を知ることができません。
参道の石の階段50段に、「文化11年(1814)三島信心講」と刻(きざ)んで
あります。これは当時大変な賑(にぎ)わいであった旧東海道三島宿の主人や
使用人、特に女郎衆が、商売繁盛、芸能上達の神としてこの祭神を崇(あが)め
、当時としては非常に高額な寄進(注)を行って、この参道の階段を整備したもの
と思われます。
その後2度の火災に遭(あ)い、昭和53年(1978)10月に、鉄筋コンクリ―ト、
銅板葺(ぶ)き、33坪の新社殿が作られました。昔は、神社の後方に「神の池」と
よばれる池があり、水がこんこんと湧いていて、地元の人々に「おみいけ」と親し
まれていました。しかし、水が少しずつ減少し、昭和40年(1965)ごろから、まっ
たく止まってしまいました。現在の徳倉4丁目防災器具倉庫のところです。
最近は神社周辺に住宅団地ができ、例祭や祭典が盛大に行われ、八乙女舞
(やおとめのまい)が奉納されています。また、神社所有地の一部に建てられた
北上(きたうえ)公民館、徳倉公民館は、市民の文化的 活動に利用されています。
(注) 神社に財産を寄付すること。
出典 『三島市誌 下巻』
p.565、『田方神社誌』 p.12、『Welcome toふじのくに三島』