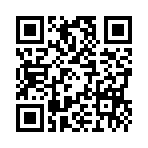≪ 居場所と出番のある地域づくりを! 皆さんの活動を応援します。!! ≫
2011年07月19日
内閣府原子力委員会委員の方のお話を伺いました。
平成23年7月16日(土)
東京の勉強会で、現在の原子力委員会委員、5名の内、2名の方の
お話を伺うことができました。(尾本彰氏、秋庭悦子氏)
冊子によると、原子力委員会は毎週1回の会合を開き、
原子力政策に関する様々な企画、審議、決定を行うとなっています。
具体的は、政策の評価、関係機関の取り組みのフォローアップ、
予算に対するヒアリングの他、世の中の動きに合わせてタイムリーに
原子力戦略の取りまとめを行っています・・・・と、書かれていました。
委員会の目的は、原子力開発利用の推進を前提にすすめられて
きたものと思います。
5名の委員の中で、特に専門性を持っている方の一人である尾本彰氏の
資料をもとにした説明が印象的でした。
尾本彰氏 プリフィール
大学で原子力工学を専攻し、東京電力㈱に入社
原子力発電所の計画設計に建設に従事し、原子力技術部長を経て
国際原子力機関(IAEA)原子力発電部長 帰国後 東京大学特任教授

 インターネット検索 以前の福島第1原子力発電所
インターネット検索 以前の福島第1原子力発電所
尾本氏のお話では
1.3.11地震と津波
2.原子力発電所の応答
3.恢復操作
4.環境影響
5.教訓
6.将来の課題
7.別紙 発がん物質と発がんリスク
以上について、80ページの資料をもとに、かなり専門的なデータよる
お話を伺いました。
今回の地震で、14基の原子炉で28の熱源があり、そのうち炉心損傷が
起きたのは、3基であったようです。
かなり専門的な話ですので、詳細は省きますが
印象的な内容がいくつかありました。
1.危機管理意識の低さ
アメリカでは、スリーマイル島事故、および、9.11のテロ対策として
すべての電源が切れた場合でも、冷却できる仕組みを持った原子炉の
開発をおこなってきたこと、それに対し、日本では危機管理意識がそこまでの
危機意識を十分に持たずに来てしまったために、あってはならない事故が
起きてしまった。
海外から学び実効性のあるものにする努力が、十分ではなかった。
2.質問 今後、水蒸気爆発は起きるか
答え 起きない
水蒸気爆発は、高温であるのものが急に冷やされて起きる。
すでに、冷却水でかなり温度は下がっているので、起きない。
3.質問 炉心溶融は起きているか?
答え 誰も、現場で確認することはできていないので
どの程度溶けているか、わからない。
4 質問 原子力発電所は、配管を現場で溶接して作り
その距離が何キロにも及ぶとすると、建屋や原子炉の
耐震性を強化しても、配管は震度の強度耐えtられないのでは
ないのか
答え 現場で溶接するのは事実だが、だから耐えられないとは言えない。
5.質問 ウランの扱いが難しいとすると、ほかの原料で原子力発電所をつくる
計画などは、話し合ったことがあるか
もっと小型で、低温で安全に発電できる実験が成功していると聞いてが
いかがか?
答え トリウムによる発電であると思うが、トリウムを原料として作ることに
課題もある。
大変、専門的なデータをもとに説明されたので、十分理解できたとは言えませんでした。
「ベント」対する誤解も対応時にはあったように、このような専門家でも判断に迷うような
事態に、最終的には政府が判断し危機管理を行うとしたら、政府関係者は素人の域は
でないと思いますので、とても怖ろしいことであると改めて思いました。
起きるかもしれない・・必ず起きるであろう東海沖地震に備え、私たち静岡県人は
浜岡原発をどうすべきか・・結論を出していくべきだと思います。
それは、単に止める、動かすだけでなく…自分たちの生活、経済、すべてへの影響を
相当な覚悟をもって考え直し、結論を引き受けていくことが必要だと思います。
東京の勉強会で、現在の原子力委員会委員、5名の内、2名の方の
お話を伺うことができました。(尾本彰氏、秋庭悦子氏)
冊子によると、原子力委員会は毎週1回の会合を開き、
原子力政策に関する様々な企画、審議、決定を行うとなっています。
具体的は、政策の評価、関係機関の取り組みのフォローアップ、
予算に対するヒアリングの他、世の中の動きに合わせてタイムリーに
原子力戦略の取りまとめを行っています・・・・と、書かれていました。
委員会の目的は、原子力開発利用の推進を前提にすすめられて
きたものと思います。
5名の委員の中で、特に専門性を持っている方の一人である尾本彰氏の
資料をもとにした説明が印象的でした。
尾本彰氏 プリフィール
大学で原子力工学を専攻し、東京電力㈱に入社
原子力発電所の計画設計に建設に従事し、原子力技術部長を経て
国際原子力機関(IAEA)原子力発電部長 帰国後 東京大学特任教授

尾本氏のお話では
1.3.11地震と津波
2.原子力発電所の応答
3.恢復操作
4.環境影響
5.教訓
6.将来の課題
7.別紙 発がん物質と発がんリスク
以上について、80ページの資料をもとに、かなり専門的なデータよる
お話を伺いました。
今回の地震で、14基の原子炉で28の熱源があり、そのうち炉心損傷が
起きたのは、3基であったようです。
かなり専門的な話ですので、詳細は省きますが
印象的な内容がいくつかありました。
1.危機管理意識の低さ
アメリカでは、スリーマイル島事故、および、9.11のテロ対策として
すべての電源が切れた場合でも、冷却できる仕組みを持った原子炉の
開発をおこなってきたこと、それに対し、日本では危機管理意識がそこまでの
危機意識を十分に持たずに来てしまったために、あってはならない事故が
起きてしまった。
海外から学び実効性のあるものにする努力が、十分ではなかった。
2.質問 今後、水蒸気爆発は起きるか
答え 起きない
水蒸気爆発は、高温であるのものが急に冷やされて起きる。
すでに、冷却水でかなり温度は下がっているので、起きない。
3.質問 炉心溶融は起きているか?
答え 誰も、現場で確認することはできていないので
どの程度溶けているか、わからない。
4 質問 原子力発電所は、配管を現場で溶接して作り
その距離が何キロにも及ぶとすると、建屋や原子炉の
耐震性を強化しても、配管は震度の強度耐えtられないのでは
ないのか
答え 現場で溶接するのは事実だが、だから耐えられないとは言えない。
5.質問 ウランの扱いが難しいとすると、ほかの原料で原子力発電所をつくる
計画などは、話し合ったことがあるか
もっと小型で、低温で安全に発電できる実験が成功していると聞いてが
いかがか?
答え トリウムによる発電であると思うが、トリウムを原料として作ることに
課題もある。
大変、専門的なデータをもとに説明されたので、十分理解できたとは言えませんでした。
「ベント」対する誤解も対応時にはあったように、このような専門家でも判断に迷うような
事態に、最終的には政府が判断し危機管理を行うとしたら、政府関係者は素人の域は
でないと思いますので、とても怖ろしいことであると改めて思いました。
起きるかもしれない・・必ず起きるであろう東海沖地震に備え、私たち静岡県人は
浜岡原発をどうすべきか・・結論を出していくべきだと思います。
それは、単に止める、動かすだけでなく…自分たちの生活、経済、すべてへの影響を
相当な覚悟をもって考え直し、結論を引き受けていくことが必要だと思います。
Posted by 野村りょう子 at 20:15│Comments(0)
│原子力事故
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。