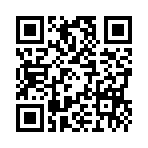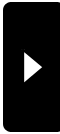≪ 居場所と出番のある地域づくりを! 皆さんの活動を応援します。!! ≫
2023年02月12日
原発寿命を延ばすのは本当に安全でしょうか。
石油、天然ガス等の不足による電力価格の高騰がら
公共施設や病院、介護施設などの光熱費の負担が大きくなり
公共サービスを継続していくのも、大変な状況になるつつあります。
そのような中で、原発の再稼働や新設することも必要性ではないかと
慎重論から推進に向けた意見が出てきました。
本当に安全な原発が建設できるのであれば、問題がないですが
東日本大震災以来、厳しくなった安全性への基準をクリアーするには
高度な技術と膨大なコストと時間がかかるようです。
そんな中で、国が打ち出した既にある原発の寿命を40年から60年にしようと
いう取り組みは、安心安全なエネルギー政策といえるのでしょうか。
以前、東芝機械に勤務され、福島第1原発の設計にも関わった方から
聞いた話を紹介します。
「原発は配管のお化けです。原発本体が地震に耐えられても、
配管が持ちません。
設計通りにはいかないこともあり、配管は現場で溶接するするので
その溶接などが、地震に耐えられるかどうか、疑問です。」
と言われました。
40年の耐用年数を60年にして、配管は対応できるのでしょうか。
一般に、部品まですべて交換する手間暇考えると、コスト的には
新たに建設した方が早いし、安く済むと思うのですが、このコスト意識は
あるのでしょうか。
以上のことを考えると、耐用年数を40年から60年というのは、古い原発に関しては
余程、慎重に考えるべきと思います。
泊原発の再稼働にも、原子力規制委員会から厳しい意見が出されているようですね。
https://www.htb.co.jp/news/archives_19031.html
2013年05月05日
三島市:原発は日本で安全性が確率出来ていないのに、外国には売るの?
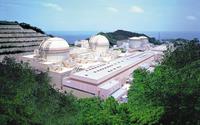
< 原発産業の今後 >
国内の原発がすべて停止し、安全性が確率されないままで
再稼働のメドがたっていません。
設置した地方自治体では、再稼働を望む所もあるようですが
国の税収が減る中、何千億円ものお金を払い続ける国力が今の日本にあるのでしょうか。
電力会社は、軒並み赤字経営ですが、基幹産業として潰すわけにはいかす
国が替わって補填せざるを得ない状況です。
安倍総理は、連休中に外交に力をいれ、精力的に働きかけを
行っているようです。
その効果に期待したいところです。
<原発を売るのではなく、安全に解体処理する技術を確立して、売るべき>
その中に、「トルコに原発を売る」というニュースがありました。
他の産業でしたら、大いに歓迎したいですが
日本で安全性が確立できていないままの、大事故を起こしてしまった日本が
原発を今の段階で売るというのは、どうなんでしょう。
賛同できますか?
日本人として、誇りをもって売ることができる産業に力を入れて欲しいものです。
以前、ある講師の話で
日本は、これからは
「原発をきちんと安全に解体処理する技術を確立すれば、その技術が売れる」
というのを聞いたことがあります。
世界中に広まった原発ですが、新エネルギー開発が始まり、需要がこれまでよりなくなったと
したら、造ってしまった「原発」を安全に処理する技術を確立すべきとと思います。
そして、それは処理に100年間以上続くとしたら、その技術を誇りをもって、ビジネスとし
て世界に売るべきと思います。
これ以上、原発をつくることに加担するのは、国民の合意が得られるのでしょうか。
2012年05月14日
小山町:「放射能って何だろう?」おしどりの講演会
 夫婦音曲漫才師
夫婦音曲漫才師{おしどり}の講演会に参加しました
おしどりのブログアドレス
http://oshidori.laff.jp/
日時 平成24年5月13日 14時~
場所 小山町総合文化会館 菜の花ホール
主催 おやま町民会議
そもそも、なぜ、漫才師が放射能?という話から
大阪から東京に出てきた直後に東日本大震災を体験
その後の、福島第一原発事故の公開される情報に疑問を持ち
東京電力の会見場にも参加。
その情報をブログで伝える・・・などしているうちに、漫才師のネタとして
話すようになり、講演会として呼ばれるようになったようです。
マコさんは、そもそも、鳥取大学医学部中退。
医学部に在籍していたときに学んだ内容との違いに、東電や国が
発表する内容にい不信をもち、原発に近い飯舘村の住民や、子どもたち
への支援にも関わる。
飯館村の子供たちが、震災時に適切な避難をしなかったため
(行政の避難指示が間違っていた)
どれくらいの放射能を浴びてしまっているのか、検査して欲しいと要望を
出したが、すぐに検査されなかった。
直後(3ヶ月以内)でなければ検査できない「放射性ヨウ素」に
どれくらい被爆したのか不安を抱えている親子も多かったのに
その期間はされなかったようです。
被災して、その後も不安を抱えたまま過ごす事は、本当に辛いことです。
福島第一原発に近い地域の人たちは、風向きで線量の多い地域に
移動してしまったり、距離があるからと安易に外で遊ばせてしまったり
間違った指導、情報で被爆量が増えてしまいました。
今も、内部被爆の不安を抱えて過ごしている地域の皆さんに
私達は、何が出来るのでしょう。
今後も、考えていきたいと思います。